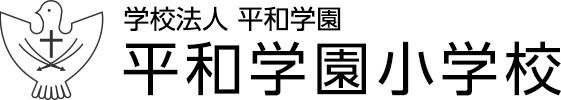一月最後の週はじめ、児童礼拝のお話は学園宗教主任である児玉先生でした。
『イエスさまは生きるのに、私たちが大切にしなければならないことを二つ言われました。
一つは「神さまを愛すること」もう一つは「隣の人、隣人を愛すること」です。
今日の聖書の個所で、イエスさまのところに来た律法学者にこう言っています。
「心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くすささげものやいけにえよりも優れています。」たくさんのお金を持っていて、神殿で牛や羊をささげものにする人がいました。たくさんのお金をささげる人もいました。でも、イエスさまはそんな大きなささげものよりも、神さまを愛して礼拝し、隣人を自分のように愛することがずっと素晴らしいと言われました。
隣人を愛するというのはどういうことか。平和学園小学校のみなさんはよく分かっていると思います。隣人愛献金をしていますね。
先日、私が能登半島に行くので、小学校で献金を能登半島の教会のためにささげてくれましたね。たくさんの献金をすることができて、教会の方たちも喜ばれていました。
能登半島は、ここからとても遠い場所にあります。朝8時半の電車に乗っていきました。金沢駅に着いたのは12時半でした。能登半島はそこからさらに2時間くらいかかります。
遠い場所にいる人たちのことを、隣人と思うことはとても難しいですね。会ったことも無いしどんな生活をしているのかも分かりません。でも、みなさんは今自分ができる精一杯の献金をしました。それは、会ったことも無いし、住んでいる場所も遠いけれども、きっと困っている。だから助けたいという思いで献金をしてくれたのだと思います。
それが隣人を愛するということです。
愛するというと、すぐそばにいて、いろいろな事をしてあげるというイメージがあると思います。すぐ隣にいて助けることも大事なことです。でも、会ったことの無い人たちのことを思って、彼らに何が必要かを一生懸命考えて、今できることを精一杯することも愛するということだと私は思います。
今回、能登半島に行ってみて思ったのは、人が町に居ないということでした。地震で壊れた建物の工事をする人たちがたくさん居るということも無く、まだガタガタの歩道を歩いていてすれちがうのは、ほんの数人でした。みんな住めなくなってしまったので、違う場所に移ってしまった人が多くいるのだと思います。建物が新しくなれば帰ってくる人もいると思います。
でも、一年も建物が直らなくて、他の場所に住んでいたら、もう一度戻るというのは時間が経てば経つほど難しくなってしまいます。
今回、能登鉄道という電車に乗りました。その電車はかたりべ列車といって、ガイドさんが地震の時の状況をお話してくれます。そのお話を聞きながら、能登の風景を見ることができました。元々その電車は観光列車だったので、ガイドさんは能登のきれいな風景を紹介する人でした。
《能登列車のかたりべさんのお写真》
しかし、地震の日、電車に乗っている時に地震が起きて慌てて電車に乗っていたお客さんたちを高台へと避難させたそうです。その日は近くにあった小学校に避難してお客さんと一緒に夜を過ごしたそうです。自宅に帰ってみると家は壊れてしまって住めなくて、今は仮設住宅に住んでいます。
《車窓から 屋根の穴にソートをかぶせてある家々》
でも、能登のために何かをしたい、どうにかふるさとをもとの風景に戻るように何かがしたいという思いで、一生懸命地震の時のこと、能登がどんなに素晴らしい場所かを語るかたりべとなって県外から来た人たちに伝えてくださっています。能登が大好きだからこれからも頑張っていきます、と言っていました。
次に能登のために出来ることは何でしょうか。私自身も今、次に何ができるかを考えています。一人が出せる献金は少ないかもしれません。でも、今回みんなで集めたらたくさんになりました。学校でできることはまだまだありますね。それを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。』