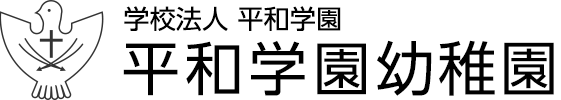子どもたちの園生活はリズムを段々と取り戻し、2学期の大きな行事のひとつである運動会へ心が動き、活動が始まりました。
今回はその運動会について少し違った視点から皆様に知って頂こうと思います。
子どもたちは運動会という大きな行事の前でも、沢山の遊びを繰り広げながら幼稚園生活を過ごしています。例えば、泥遊び、おままごと、モノレール作り、サッカーなどその遊びは様々です。
ではなぜこの行事が迫った時期に子どもたちは沢山遊んでいるのでしょうか??なぜこの遊びが必要なのでしょうか??各学年の様子と絡めて説明して運動会と日々の遊びの関係をお伝えします。
年少組
年少組の子どもたちは幼稚園に入園して、まだ半年しか幼稚園生活を経験していません。その子どもたちは本当に遊び中心の園生活をおくっています。どのような遊びを経験し、毎日を過ごしているのでしょうか。
最近よく目にするのはお祭りごっこです。お面屋さん、あめ屋さんなど年中組の子どもたちをお客さんにして遊んでいます。
ではこの年少組の子どもたちは運動会の経験がない中で、どのように運動会を行っていくのでしょうか。やはりそこで重要になるのが「遊び」なのです。
「遊び」の経験をこの半年の園生活の中で重ね、「こんなことをしたら楽しいのではないか。」ということを教師は子どもたちの内側から見つけていきます。毎日の遊びが、そのまま競技になっていくことで子どもの不安や心配が少しでもなくなれば楽しい運動会の思い出ができるでしょう。
そして年少組の子どもたちの競技は教師、年長組の子どもたちの力で支えられたくさんの種がまかれて、成長へとつながります。
年中組
年中組の子どもたちは、一度運動会を経験している子どもがほとんどです。
その中で年中組の子どもたちにも「遊び」はとても重要な役割をします。年少組の頃に比べ、ダイナミックに、より幅広く遊びを行っている年中組の子どもたち。
「運動会でどんなことがしたい?」と質問すると、「トンネル掘り」「モノレールつくり」「電車ごっこ」「楽器がやりたい」「ダンスを踊ったらいいんじゃない」「恐竜になって競争がしたい」「ライオンになって輪をくぐったらいいんじゃない」など色々な経験をもとに、やりたいことが目白押しです。その遊びをベースに子どもたちの内側から出てくる意見を、というベースに教師がアドバイスをし、オリジナル競技が完成します。加えて、玉入れ、大玉転がしなどいわゆる運動会という競技を行います。来年の年長組になったときのため、種をまき、成長につなげていきます。
これが1年間の遊びの経験、生活の経験の違いです。日頃の遊びから競技を見つけ出す、本園ではやはり「遊び」が重要なようです。
年長
年長組ではどのように「遊び」が関わってくるのでしょうか。
年長組の子どもたちはもう二度も運動会を経験しています。「やっと僕らの番だ!!」と張り切っている子どもも少なくはないでしょう。
年長組の子どもたちに年中同様「運動会でどんなことがしたい?」と質問すると、年中組のそれとは比べられないくらいの競技意見が出てきます。その数なんと100個以上です。
やはりそれほど年長組になるまでの経験は大きいのでしょう。「遊び」の幅、「遊び」の質、日頃の様々な経験が子どもたちをここまで大きくするのでしょう。
今年の子どもたちは「チャンバラ」「ピンポンダッシュ」「クッキー作り」などのユニークな意見も出たようです。
その中からいったいどのような競技が子どもたちの手で生まれてくるのでしょうか。とても楽しみです。年中組の競技作りと異なり、そのほとんどが子どもたちの声で構成されていきます。「運営」という面でも年長組の力が発揮されます。
「運動会の前になんでこんなに遊んでいるのだろう??」と感じるかもしれませんが、子どもたちの意見・発想は「遊び」の経験がものを言うのではないでしょうか。思いっきり遊んだ子どもたちが作り上げる運動会が今年はどのようなものになるのか。今から本当に楽しみです。
今年の運動会は、10月20日(土)です。ちいさい子どもたちが参加できる競技もご用意しています。ぜひご覧に来てください。お待ちしております。